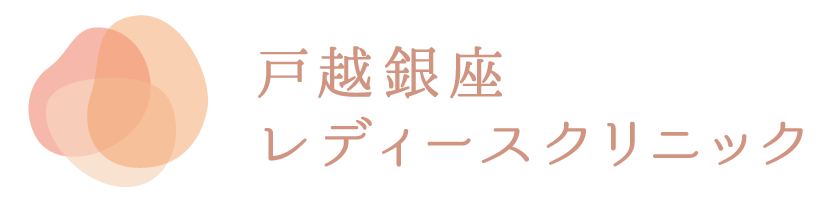ピルは女性の避妊や月経に関連したトラブルの改善など様々な目的で使用されており、ここ数年で徐々に認知されてきています。ピルは月経困難症に対して保険で処方することができます。月経困難症とは女性の生理中に生じるお腹の痛みや身体の不調のことを指します。症状には個人によって大きく異なりますが、主に下腹部痛・吐き気・頭痛・めまい・下痢もしくは便秘・疲れやすさ・イライラなどがあります。
また、月経困難症は原因により2種類に分けられます。診察では明らかな病気は認めないが、生理的な変化やホルモンバランスの変化により生じる機能性月経困難症と子宮内膜症や子宮腺筋症、子宮筋腫などの病気が関連している器質性月経困難症があります。
いずれの種類にせよ生活の質に悪影響を及ぼしている場合は保険診療でピルを処方でき、症状の改善が見込まれます。症状がひどい場合や日常生活に支障をきたしている場合には一度産婦人科医に相談することをおすすめします。
「ピルを飲んでみたいけれど、どれを選べばいいかわからない」という方も、まずは相談だけで大丈夫です。あなたの毎日をより快適にするための選択肢として一緒に考えていきましょう。
ピルについて
ピルとは?
ピルは、卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲスチン)という2種類の女性ホルモンを配合した薬剤です。ピルは自然な排卵を抑制し、子宮内膜の成長を抑制する効果があります。この効果を利用して自費では避妊目的に、保険診療では治療目的に使用されています。治療目的である保険診療で処方される低用量ピル/超低用量ピルには一定の避妊効果はありますが、避妊ピル(自費診療)には劣るとされています。(低用量ピル/超低用量ピルのパール指数は0.19~2.98に対して避妊ピルでは0.073~0.085)
ピルの種類
ピルには大まかに自費診療の避妊目的に、保険診療の治療目的に使用されています。避妊目的ではOC(Oral Contraceptive)、治療目的ではLEP(Low dose Estrogen Progestin)という呼び名になりますが、成分としてはほとんど同じであり、商品によってホルモンのが含有量がことなります。
ピルにはエストロゲンの量やプロゲステロンの種類、服用スケジュール、服用日数によってさまざまな商品があります。大きな違いとしては含まれているプロゲステロンにより世代で分けられます。
- 第1世代ピル(三相性)
- エストロゲンとしてエチニルエストラジオール(EE)とプロゲステロン(P)としてノルエチステロンが含まれています。
自費薬品名: シンフェーズ
保険薬品名: ルナベル、フリウェル - 第2世代ピル(三相性)
- EEとPとしてレボノルゲストレルが含まれています。第一世代と比較して、血栓症のリスクが低く副作用が少なくなる傾向があります。
自費薬品名: トリキュラー・アンジュ・ラベルフィーユ
保険薬品名: ジェミーナ - 第3世代ピル(一相性)
- EEとPとしてデソゲストレルが含まれています。第一、第二世代と比較して、吐き気などの副作用が低く、継続的な使用時に起こる安全性が高いとされています。
自費薬品名: マーベロン・ファボワール - 第4世代(一相性)
- EEとPとしてドロスピレノンが含まれています。他のピルとの大きな違いは男性ホルモン(アンドロゲン)作用がないためニキビなどの肌トラブルが少ないとされています。アリッサに関してはいままでのEEと異なり天然型エストロゲンが含有されているため、副作用や合併症の頻度低くなることが期待されています。
保険薬品名: ヤーズ・ドロエチ・アリッサ
ピルの錠剤は28日型の自然の生理周期と同じにするため、通常28錠または21錠が1枚のパッケージに含まれています。1日1錠ずつ服用しますが、最後の7日間または4日間はホルモンの含まれない非有効剤もしくは休薬となります。初回のピルは生理の1日目から5日目の間に内服を開始します。
どんな診察?検査は?ピル処方希望時の診察の流れ
受付後、問診に回答いただきます。
現在の悩み(生理痛、月経不順、月経困難症)、過去の病歴や現在服用中の薬、喫煙の有無(血栓症リスクを確認するため重要です)など
診察時にピル内服となった場合は、診察後に問診の回答、血圧・体重の計測をしていただくこともございます。
問診票に基づき、医師がお話を伺います。
【お悩みの確認】
症状や既往、ご本人の希望に合わせて最適なピルの種類をご提案します。
【副作用・注意点の説明】
飲み始めの吐き気や不正出血、血栓症のリスクなどをお伝えします。
ピルを内服されている方は安全に飲み続けていただくために定期的な検診をお願いしています。
・血液検査(年に1回)
・超音波検査(年に1回)→品川区在住の方は2年に1回、区の助成で検査が可能
・子宮頸がん健診(2年に1回)→品川区在住の方は2年に1回、区の助成で検査が可能
これらの検査が必要となります。(※ピルの種類によって推奨される検査等は変わります)
会社の健診や他院で行っている場合は、そちらの結果でも代用可能です。
初めてのピル内服・ピルが変更となった場合、副作用などの確認のため初回は1シート(1か月分)の処方とさせていただきます。
1か月後、内服開始後も問題がないことや採血結果などもふまえて長期処方やピルの変更を相談します。
ピル内服中に気を付けるべきことピルの3大副作用
ピルの重要な副作用①ピルの副作用:静脈血栓塞栓症
ピルの副作用の中で最も注意すべき重篤な病気として静脈血栓塞栓症があります。飛行機に長時間乗ることで起こる「エコノミー症候群」で知られている病気となります。静脈血栓塞栓症とは血液を心臓まで血液を送る深部静脈と呼ばれる血管に血栓(血の塊)ができた状態のことです。この血管は主に足にあります。そのため入院中や飛行機の上など長期間同じ体勢をとっている場合に下半身の血液の流れが悪くなり、血栓ができやすくなります。ピルを使用していると、薬に含まれる女性ホルモンのエストロゲン作用で血が固まりやすくなる傾向になります。静脈血栓塞栓症の症状は胸の痛み、呼吸のしづらさ、頭痛、しゃべりづらさ、ふくらはぎの痛みやむくみがあります。また肥満(BMI)・喫煙・高齢女性・静脈血栓塞栓症の家族歴・手術前後の方・産後前後の方も副作用のリスクが重複するためピルの使用は禁忌もしくは医師の慎重な判断のもとで投与が行われます。
静脈血栓塞栓症はピルの重篤な副作用であるため長い期間に渡り使用する場合は採血を用いた定期的な健康診断を受けることが望ましいです。
ピルに起こることが多い副作用②ピルの副作用:不正性器出血
ピルを開始してみたものの途中で中止してしまう副作用で最も頻度が高いのが不正性器出血となります。ピルを使用開始した人の20%が経験するとされています。ただし多くの場合は使用を継続できます。そして使用を継続していると、不正性器出血も次第に減少することがわかっています。不正性器出血の副作用が見られた場合には自己判断で中止せずに一度産婦人科の主治医に相談してみましょう。
その他の副作用③ピルの副作用:吐き気
ピルの副作用で見られる頻度として2番目に多いのが吐き気です。使用を続けることによって1~3ヶ月ほどで次第に症状がおさまることがほとんとです。ピルの内服を就寝前にするなど工夫してみるのも良いでしょう。またピルには第1世代から第4世代までさまざまな種類があります。種類・商品により含まれる成分も異なるため、ピルの種類を変更することにより使用できる可能性があります。副作用で吐き気がある場合は一度主治医に相談してみましょう。
ピルの内服中はいつでも相談できるかかりつけ医を決めておくことも大事です。飲み忘れや薬の内服中に判断に迷う場合は主治医に一度相談するようにしましょう。
ピルの内服についてよくあるご質問
休薬期間に出血がない、大丈夫?
ホルモンの作用が安定することにより、子宮内膜が厚くならないことがあります。そのため休薬期間中の出血が少なかったり出血がないこともあります。ピル内服中の休薬期間において出血がなくても心配はいりません。妊娠の可能性がある方は、妊娠検査薬の使用をおすすめします。
薬を飲み忘れた
ピルを飲み忘れることにより、避妊効果や病気の治療効果は下がります。また、不正出血など予期せぬトラブルが起こる可能性があります。性交渉がある場合は必ず避妊をしましょう。
薬の飲み忘れに気づいたときにはすぐに1錠を内服し、当日分の1錠もいつもの時刻に飲みます。
2日以上内服を忘れた場合は、気づいた時に前日分の1錠を飲み、当日分の1錠もいつもの時刻に飲みます。
※1日に2錠より多く飲むことはありません。
ニキビは治る?
ピルはホルモンバランスを整えることで、ニキビや肌荒れの改善が期待できます。内服の種類も関係あるので、主治医にご相談ください。
不正出血が続いている
ピル内服開始後1〜3ヶ月は不正出血をはじめとする副作用(嘔気、頭痛など)が出ることがあります。長く続く場合や量が多い場合は他の病気が隠れていることもあります。そのため受診をおすすめします。
休薬の期間をずらしたい
出血の日を移動させたい場合は同じピルの内服を調整することにより可能です。主治医にご相談ください。
何シート処方してもらえますか?
病院によって異なりますが、当院では最大3ヶ月処方しております(自費ピルの場合は6ヶ月まで)。血栓症などの合併症リスク観点から定期的な検診を受けながら内服を継続することが大切です。
妊娠しづらくなるって本当?
ピルは一時的に排卵を抑える薬です。内服を中止すれば自然に排卵が戻り、妊娠が可能になります。将来の妊娠率に悪影響はありません。